- Railway Museumトップページ・サイトマップ
- 近畿日本鉄道
- 鮮魚列車トップページ
鮮魚列車とは
鮮魚列車とは、魚介類を運ぶ行商人専用の貸し切り列車(以下、鮮魚列車)です。
かつては、一般車両の一部に荷物室を設置した「荷物車」が各地に走っており、
手荷物や新聞、野菜、魚介類等の輸送が行われていました。
しかし、魚介類を車内に持ち込むと悪臭で他の乗客に迷惑になるため、
専用列車を運行する必要が出てきました。
1963年、「伊勢志摩魚行商組合連合会」の貸切列車(*)として運行を開始、現在に至ります。
(*)鮮魚列車は、上記の会員以外の乗車は禁止されています。くれぐれもご注意を。

現在運転されている鮮魚列車、2680系
長瀬にて
運行について
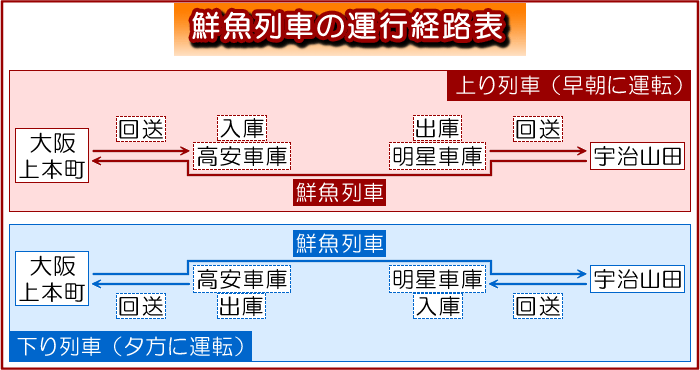
鮮魚列車の運行は上の表のようになります。
停車駅は、
鶴橋、大和高田、大和八木、桜井、榛原(はいばら)、名張、桔梗が丘、伊賀神戸(いがかんべ)、 榊原温泉口(さかきばらおんせんぐち)、伊勢中川、松阪、伊勢市
です。
車両について
前述の通り、魚介類の悪臭対策のため、専用の車両を使用します。
新型車両ではなく、やや古い車両を改造して使用しています。
車体色は伝統的に赤を基調に、1481系以降は白帯を巻いたものとしています。
長距離運行のため、一部の車両にトイレが設置されています。
専用車が検査等で運行できない場合は一般車を使用します。
車両解説は車両紹介のページへどうぞ
(*)車両形式をクリックすると、車両紹介のページにジャンプします。
現在は
最盛期は100人を超える利用者がいましたが、自動車の普及、高速道路の整備等により現在は
半数以下になってしまいました。近鉄では、地域の足として今後も運行していく予定だそうです。
鮮魚列車は国鉄(JRの前身)をはじめ多数走っていましたが、現在は近鉄が運行するのみとなっています。
今後の活躍を祈るばかりです。
